
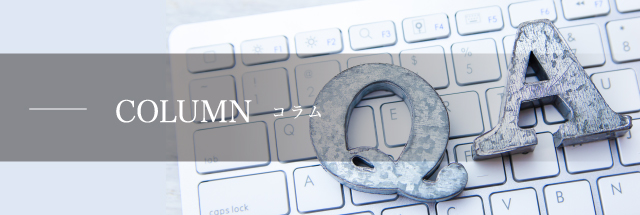

日本でガバナンスが注目されたのは2000年以降ですが、その理由は大企業やその子会社による粉飾決算や労働基準法違反といった不祥事が相次いだためです。
最近では、さまざまなコンプライアンス違反などが取り上げられ、そのことが企業の業績悪化を加速させるため、企業にガバナンスを求める声が大きくなっています。
ガバナンスとは「統治・支配・管理」を意味する言葉ですが、企業視点では、「コーポレートガバナンス」の意味で使われることが多く、この場合は健全な経営をおこなうための管理体制や企業統治のことを指します。
ガバナンスを強化させることは、企業にとって社会的信頼性を高め、持続的な成長力、競争力を向上させるためには不可欠なものです。
ガバナンスを強化するためには、プラスの企業文化を育てることが重要な課題であり、企業の成熟度を高める必要があります。
企業文化は空気と同じで、目には見えませんが、組織のすみずみまで行き渡っています。
だからこそ、その文化が、情熱、活力、献身、寛大な精神、創造性で満ち溢れていれば、その空気を吸っている従業員は、強く影響され、その熱意がお客様にも伝わり、素晴らしい「共生の関係」に磨きがかかっていきます。
企業文化とは、「心理社会的インフラ」ともいえ、そこに盛り込まれている共通の価値観が、組織の人々を巻き込んで、共通の目的のためにしっかりまとまり、チームとなって、その力が企業のエネルギーとなっていきます。
ダニエル・ピンクは、これからの時代は「ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代」で、「コンセプトの時代」を「創意や共感、そして総括的展望を持つことによって社会や経済が築かれる時代」と定義し、「情報化時代」に代わるものと位置付けています。
さらに、論理的観点から感情的・直観的観点へと社会が移行しつつあるとも語っています。
そして「コンセプトの時代」の大切な6つの感性を、デザイン・物語・調和・共感・遊び・生きがいであるとも言っています。
企業は確かに事業が順調でなければならないし、利益も上げていかなければなりません。
しかし、数字だけを追い求めていたら、やはり持続可能な組織、今回のタイトルでもある「愛される企業」にはなりません。
経営陣と従業員の協力があり、お客様やサプライヤー、地域社会ともしっかり「コミュニティ」を創り、社会の課題解決をしながら社会貢献していくことが、あたりまえですが、企業の存在理由と言えるのではないでしょうか。
企業の成熟とは、まさに「愛される企業」になることだと思います。
そして、時には業界の常識を疑い、新しい価値創造をしながら長期的な観点で事業を行い、「人」を大切にしながら、何のために存在しているのかを考え続けるリーダーが「愛される企業」を創り上げていくのだと思います。