
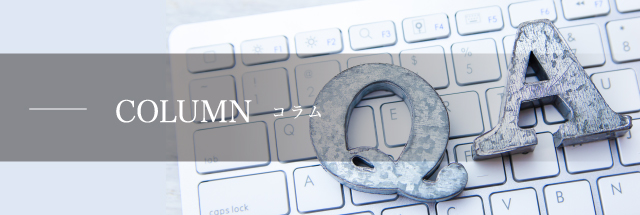

私は、講義で必ずこの言葉を最初に投げかけます。
「最小人数で最高パフォーマンスをあげるには」と。
この課題に取り組むには、今までのやり方を見直す必要があり、そしてやり方を見直すためには、ものの見方を大きく変える必要があります。
優れたデザインは、複雑で無駄に満ちた世界を、シンプルで有意義な世界に変えてくれるように、私たちは、組織のデザインを変えていく必要があるのではないでしょうか。
講義の中で、「無駄な忙しさは何ですか?」という問いでよく受講生の皆さんにワークをやっていただいていますが、無駄な仕事が日常の中で、より重要な課題に取り組む時間を阻んでいることがわかります。
わかっていても、断捨離できないし、もしくはどのように断捨離すればよいのか、組織のしくみができていないことがほとんどです。
慣れしたしんだやり方から抜け出せないのは、人間の本能です。
新しいやり方を考え実行することを脳は苦痛と感じますし、心配症が強い日本人は、例えば、DX化したはずなのに、未だにペーパーを打ち出し保存するというダブルスタンダードを残しがちです。
多くの受講生が、おかしいと思いながらも、不満に感じながらも、無駄な時間に疲弊しながら、諦めてしまうことが組織においての大きな課題だということをもっと強く認識する必要があるのではないでしょうか。
では、どのような考え方が必要かといえば、まず「選択する力」を強化しなければなりません。
私たちは、時間とエネルギーの使い道を選べるにもかかわらず、何故か選択することを後回しにしてしまいます。
だからこそ、多くのルーティンで行われている仕事を疑い、どのような仕事が重要で正しい時間の使い方なのかを見極めなくてはなりません。
そして何かを選ぶということは、何かを捨てることに繋がっていきます。
「あれもこれも全部やる」というのは、とても欲張りなことで、組織において捨てるべきものは何かをしっかりと考えなければ、どれも中途半端に終わってしまいます。
これから、お客様に選ばれなければ、ますます持続的な企業の継続が難しくなる時代だからこそ、捨てる勇気も大切です。
そして努力と根性でやりとげるのではなく、効果的なやり方で実現する「しくみづくり」が、より組織を強くしてくれるはずです。
この考え方は、「努力」を否定しているのではなく、「努力」の方向性や考え方が間違えないことが大切だということです。
「見極める」「捨てる」「しくみ化する」は、1つの輪のようにサイクルになっています。
このサイクルを回し続けることによって、得られる成果が大きくなれば、組織の成長に繋がり、従業員の皆さんのモチベーションにも繋がっていくはずです。
人口減少が避けられない日本だからこそ、「最小人数で最高パフォーマンス」を目指すことは、これからの未来を創る大きなチャンスだと私は考えています。