
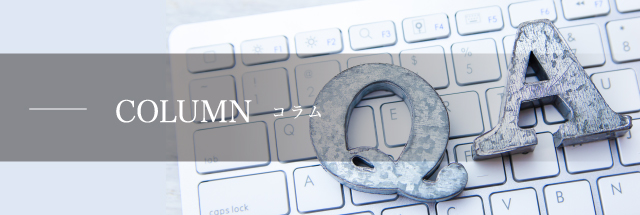

我々中小企業診断士は経営者と話す機会が多いため世の中の様々な産業の実態や経営者それぞれの考え方に触れる場面が多くあります。
最近感じることは若手経営者は以外と「楽観的」な方が多いことに驚いています。
楽観的という言い方は優しい表現ですが、厳しく言い方をすると「危機意識が足りない」と思える方が少なくありません。
特に2代目、3代目の家族経営者は先代が築いたビジネス路線に乗っかり、子供のころから父親の経営者像を見ており、従業員がいて、設備や店舗があり、取引先からの受注があるという状態で事業を引き継いでいますので、経営面での詳しい数的ヒアリングを嫌うという感情も一定の理解はできます。
一方で経営支援を生業にしている私たち中小企業診断士は常に企業の経営課題を探し改善しようとする感情のクセがあります。
それを良いことであると信じるあまり、もしかすると企業のアラ探しをしている可能性もあります。
その感情のぶつかり合いについて一度立ち止まって考えてみましょう。
支援者側の思考回路は次の通りです。
「出会った会社を良くする」という使命感に浸り、まず会社の現状確認⇒次に問題点抽出⇒課題抽出と改善方針⇒改善計画⇒実行計画⇒実行⇒検証・・・・。
おおよそこんな感じです。
これを企業と二人三脚で進める活動を「伴走支援」と呼び無意識に自己ニーズを満たしています。
経営改善を最優先で重視するあまり、時には経営者に指導したり厳しい現状を突き付ける場面も少なくありません。
さてここで疑問が生まれます。
はたしてこのような支援者の言動は経営者からどう映るのでしょうか。
日本中のほとんどの中小企業は問題だらけです。
別の言い方をすると一人の経営者で解決できる能力は限られています。
また先代から経営すべてを引き継いだ場合、すでにある経営資源を使わなければならない制約があり、そこを中小企業診断士から指摘され、ほじくり返されても経営者としてダメ出しされた感覚になるのではないか、ましてや初対面の診断士からの指摘はマイナス感情しか生まれません。
ではお互いの感情一致や不一致はどこで分かれるのでしょうか?
それは出会いのシチュエーションによるものです。
例えば銀行に借入相談に行く場合、銀行側から厳しく経営状況を質問され数値を指摘されながらでも借入を目指す経営者のニーズは資金繰りにあるため銀行ニーズと一致しています。
逆にセミナーで出会った中小企業診断士からいきなり正しくも厳しい指摘がなされたら、経営者感情は乱れます。
話を戻します。危機意識が足らず楽観的な経営者に出合ったら、支援者はどのようなアプローチが求められるでしょうか?
その答えは私の中ではひとつです。
どんなシチュエーションでもその経営者が本気で会社の将来を思っているのであれば、楽観的になっている真意を突き止め、その立場を理解し、短時間でこちらの話を聞く関係を築き、安易な楽観視を打ち砕き危機意識と同時に解決案を提示することになります。
私たち支援者と名乗る立場の人間も経営者と同様お互いの共通目標と達成したい共通感情を認識できれば、違う立場で役割分担する仲間同士として協働できるはずです。
そこで初めて伴走支援らしき形がスタートします。
診断士の正義だけの主張では、支援ビジネスとしては成り立ちませんので、顧客やクライアントへの敬意を十分払った上でのバランス感覚が必要です。
中小企業診断士も経営者の一人ですので誰かからダメ出しされたらイヤですよね。これからも常に謙虚でかつ強い意志を磨いていきたいものです。