
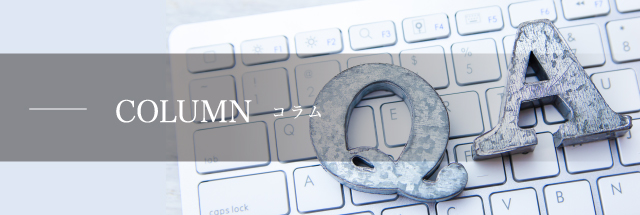

BCP(事業継続計画)があることで、災害などの緊急事態発生時にBCPを発動し、損害を最小限にとどめつつ、中核事業の早期復旧を可能とすることができます。
BCPは、以下の項目を計画で定めることをお勧めいたします。
1.基本方針
2.適用範囲
3.重要業務
4.被害想定
5.目標復旧時間
6.災害対策本部
7.初動対応
8.重要な要素
9.復旧活動
11.教育訓練
12.継続的改善
13.地域貢献・社会貢献
最初から完璧なものを策定することにこだわらずに、まずは作ってみて、実際に運用しながら計画を磨き上げていくことが有効です。
各項目について具体的に確認していきます。
1.基本方針
経営者として、従業員や取引先などの関係者に向けて、わが社がBCPを策定する目的を意思表明するものです。
2.適用範囲
BCPを適用する組織、BCP発動基準を定めます。
(1)適用する組織
BCPの対象とする会社や、工場などの施設、そして所在地を明確にします。
(2)BCP発動基準
災害対策本部を設置することとするBCP発動基準を明確にします。
例えば、
「適用する組織の所在地域において、震度6弱以上の地震が発生した場合」
などです。
南海トラフ巨大地震の発生による災害が懸念される地域では、まず大地震発生をBCP発動基準としてBCPを策定するとよいです。
そうすることで他のケースへの展開も容易になります。
3.重要業務
災害からの復旧活動において、会社にとって最も必要な業務、すなわち重要業務を決定し、優先順位をつけて限られた経営資源を投入していくことが求められます。
その重要業務の決定方法として、影響度比較表を作成して検討する方法があります。
影響度比較表とは、重要業務候補を挙げて、売上への影響、お客様への影響、社会的責任などの判断要因で影響度を評価し、総合判断する方法です。
例えば、影響度を「重大」「大」「中」「小」「軽微」の5段階で評価します。
4.被害想定
災害発生による被害状況を予想します。それにより、初動対応や復旧対応を検討しやすくなります。
被害想定の対象ですが、製造業の場合ですと
①従業員
②事務棟・工場
③設備・治工具
④在庫:材料・部品、仕掛品、完成品
⑤仕入先・協力先
⑥情報:生産や販売に必要な情報
⑦物流:材料や製品の物流
⑧インフラ:電気、通信、水道、ガス、幹線道路
を挙げることができます。
例えば、従業員に対する被害状況の予想は
「当日は緊急対応要員のみ、2日目30%、7日目までに90%出社」
というように検討します。
5.目標復旧時間
災害発生から重要業務を復旧させる目標復旧時間を設定します。
わが社の場合に考慮すべき制約条件を挙げ、それらにおける許容時間を検討し、総合的に判断します。
例えば、顧客からの要請として「BCP目標復旧時間は10日」と出ている場合は、それを考慮する必要があります。
まずはBCPの目的・目標を定めて具体的な内容を検討していきましょう。